クワガタの人工飼育が確立されて以来、常に「大きさ」というものだけが追求されてきました。
「菌糸ビン飼育」という飼育方法が出現し、確かに今まででは考えられない様な大型個体が誕生する様になりました。
が、そこには従来の飼育方法では考えられない様な「死亡率の高さ」が生じる様になりました。
そこには、「大きさの価値」しか追求されずに「死んでもいいから大きく育てば良い」という物的な考えしか存在しません。
「命より大きさを重視した飼育方法」は一般には理解不能な状態となっています。
菌糸ビン飼育は死亡率が高くて当たり前と言う業界の風潮に私自信、理不尽さを感じて真っ向反対です。
5年くらい前に一切の菌糸ビン飼育を止めて、実際に死亡率が低いとされているマット飼育のみで数千匹以上に及ぶ数の飼育を行った事が有ります。
かたくなに3年間、マットボトルだけで地元にいる普通のクワガタの幼虫の飼育をし続けました。
色々な品質やコンセプトのマットで飼育をして死亡率と大きさのデータを地道に取りました。
添加マット(小麦粉等の有機物をオガに混ぜて強制的に発酵マットにした物)は死亡率が高い物が目立ちました。
また、劣化が早く、ダメージを受ける個体が多かったです。
もう一つ、夏場の暑さで高熱の発酵と臭いガスが発生してしまった場合に全滅してしまう恐れもあります。
真夏は発送中にどうしてもマットが高温になり易く、お客様の大切なクワガタを危険な目に遭わせてしまう事にもなってしまいます。
やはり自然の生き物に人為的な「添加剤」は無理が有るのかなと感じ始めました。
これでは菌糸ビンと同じだと思い、発想を転換して「大きくならないことの代名詞的な存在」の無添加発酵マット(有機物を人為的に加えず、自然まかせに発酵マットにした物)で飼育をしてみました。
確かに大きく育ちませんが、死亡率はゼロに近い物が有りました。
それも死亡率がゼロに近い飼育結果が残せました。
ただ成長が遅過ぎるという欠点がありました。
これではあんまりだ。ということで菌糸ビン飼育のメリットとマットボトル飼育のメリットを融合させてみようということで数年前から色々な試行をしております。
ポイントは以下の4つです。
1.なぜ菌糸ビンでは死亡率が増えるのか?
2.死亡し易い飼育方法なのになぜ菌糸ビンのほうが早く大きくなるのか?
3.自然界での幼虫の生態は?
4.無添加でより自然環境に近いキノコの成分を残したマットの再現は?
結果から言います。
確かに自然界のクワガタの幼虫もキノコの菌床が大好きでこれを食べて育っています。
これに実際に山に入ることで経験したクワガタの生態と自然界のキノコの役割りのバックグランド条件を付けてみると物凄く面白いことが分かりました。
自然界の幼虫は、ある時期(終齢の成熟期)を境に菌糸を拒絶し始めることが分かりました。
これを条件に加えて、考えていると面白いことが分かりました。
人間や他の生物同様に「小さい時は高い栄養素」の物を食べて早く大きくなろうとするメカニズムが有るということです。
人間でも子供の時の食生活を大人になっても続けていると成人病になります。クワガタの終齢も同じです。
ちょっと意味合いが違うかもしれませんが、この様にとらえて下さい。
実際にはBOD(生物化学的酸素要求量)、熱量、温度などと物凄く複雑になってニッチになるので止めておきます。
そこで考案したのが、「大きく成長するまで菌糸ビン→成長しきったらマットボトル」という必要以上に高い栄養素を摂取させない自然界の循環により近い飼育方法です。
実際飼育してみると死亡率が非常に低く、納得できる成虫が生まれてきました。
ただ、種類によっては「マットボトルへの切り替えのタイミング」が難しい物が多々有り、コツをつかむまで思ったより苦戦を強いられる種類もいるのも事実です。
が、大きさを問わず成虫になった時、確実に早く元気に活動を始める事がわかりました。
これで「満足のいく元気な状態で羽化させたい」、「死なせたくない」というお客様のニーズに近付けた気がします。
また「より大きく育てたい」というニーズにお応えする為に、白色不朽菌によって朽ちた木を再現した無添加の虫吉幼虫マットを開発しました。
交換のタイミングさえ分かればオオクワガタでも大丈夫です。
最後に。
この飼育実験や自然観察で菌糸ビン飼育の「死亡率の高さ」も科学的に解明できました。
また、長期間の菌糸ビン飼育でよく起こる「セミ化(サナギになれなくなった幼虫)」や「サナギになっても無事羽化できない」などのメカニズムも分かり始めました。
クワガタの羽化の失敗はサナギの時の要因より、その前の段階の幼虫の時期の栄養価の過剰摂取に問題が有ることも分かり始めました。
成虫になる為に短期間でエネルギーの補給なしで「幼虫→サナギ→成虫」と3回も形を変えていきます。
形を変えるには物凄い物理ネルギーが必要です。
幼虫の時点で弱らせてしまうとこの「エネルギー不足」でサナギ→成虫に成れません。
弱らせない飼育方法も念頭に置き、劣悪な環境(高い温度やエサのコンディション悪化)は絶対に避けて下さい。
これも「死亡率を下げる条件」の1つです。
当店のブログには、より安心・安全に大きく育てる為の飼育のコツを惜しみなく記載しております。ぜひ参考にしてみてください。



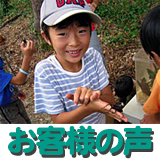








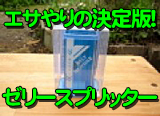
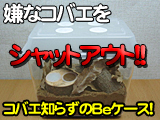


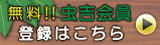







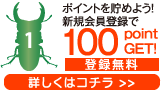
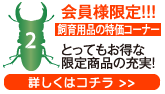
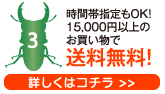

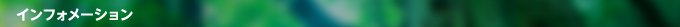


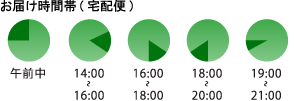
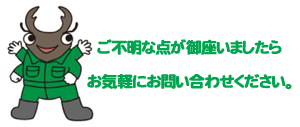

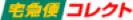



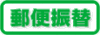
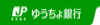
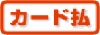
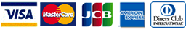
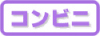
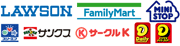

 当サイトはベリサイン社のデジタルIDにより証明されています。 データ入力、送信は、SSL暗号通信により、お客様のウェブブラウザーとサーバ間の通信がすべて暗号化されるので、ご記入された内容は安全に送信されます。
当サイトはベリサイン社のデジタルIDにより証明されています。 データ入力、送信は、SSL暗号通信により、お客様のウェブブラウザーとサーバ間の通信がすべて暗号化されるので、ご記入された内容は安全に送信されます。 