里山の甲虫図鑑
里山で見かけることが出来るコウチュウ(甲虫)の仲間を紹介したページです。
●コクワガタ

甲虫目 クワガタムシ科
大きさ(野外品)・・・オス16~50ミリ、メス18~30ミリ
自然界での活動時期・・・5~9月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
全国各地で最も多く見かける事が出来る一般的な昆虫
最も早い時期から活動する。
主にクヌギやコナラの樹液に夜間集まる。
昼間は樹皮の裏や木の洞に隠れて過ごす。
成虫は、越冬して複数年の寿命を持つ。
6から8月は夜間や早朝に樹液が出ている木を隈無く探すと比較的簡単に見付ける事が出来る。
雑木林に生息する身近な存在です。
●カブトムシ

甲虫目 コガネムシ科
大きさ・・・オス30~85ミリ、メス30~50ミリ
自然界での活動時期・・・6~8月
本州、四国,九州 ※北海道へは人為的に持込まれたとされる。
夏になると雑木林のクヌギやコナラの樹液に集まるに本最大級の甲虫。
夜行性の昆虫でオス同士が激しく喧嘩する姿がお馴染みです。
飛行性が高く街頭や蛍光灯の光にも集まる。
大きくて重たい体を空中に浮かす為、上翅と下翅の合計4枚(2対)をフル稼働させて飛ぶ。
写真の様にオスは後ろ脚を交差させる様にしてオシッコを飛ばす習性が有る。
この行動は、メスに自分(オス)の存在を気付かせる為のフェロモンを出しているとされる。
自然界では、お盆を過ぎるとエサとなる落葉樹の樹液が止まる為に数が激減する。
この時期になるとメスは産卵を済ませて力尽きてしまう事が多い。
●ヒラタクワガタ

甲虫目 クワガタムシ科
自然界での発生時期・・・5~9月
大きさ(自然界での)・・・オス39~74ミリ、メス19~42ミリ
分布・・・本州(東日本は東北南部まで)、四国、九州
平べったく固く頑丈な装甲に覆われた、挟む力が非常に強い昆虫。
成虫で越冬可能で複数年の寿命を持つ。
主に夜間、平地の雑木林のクヌギ、コナラ、アカメガシワの樹液に集まる。
縄張り意識が強く樹液が出ている付近の洞や裂け目に住み着く事もある。
その中で複数のメスと一夫多妻制のコロニーを作る場合もある。
●コカブトムシ

甲虫目 コガネムシ科
大きさ・・・18から24ミリ前後
活動時期・・・6から10月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
夏場の雑木林で稀に見掛ける黒く上翅に点刻がある小型の甲虫。
一見、ゴミムシの様にも見えるが列記としたカブトムシの仲間で頭部に小さな角を持つ。
オスとメスの違いは角の発達の他にオスの胸部が丸く大きく凹んでいるのに対し、メスの胸部は楕円形に細く凹んでいる所から区別が付く。
雑食性で昆虫(幼虫)やミミズの死骸を食べたり樹洞に溜まって腐った樹液を好む。
幼虫は朽ち木を食べて育つ。
酸っぱい臭いの樹液が出ている樹洞や根元付近を探すと見付けやすい。
●ノコギリクワガタ

甲虫目 クワガタムシ科
大きさ(野外品)・・・オス36~72mm、メス19~40
自然界での活動時期・・・6~9月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
6月の梅雨に入った頃から平地や低い山地の雑木林でよく見かける事が出来る昆虫。
主に夜間や早朝にクヌギやコナラの樹液に集まる。
小型の物は、真っすぐなアゴになるが、大型になればなるほど水牛の様な立派なアゴを持ちます。
メスは、丸みを帯びた体型をしている。
●カナブン

甲虫目 コガネムシ科
大きさ・・・22~30ミリ
活動時期・・・6~8月
分布・・・本州、四国、九州
梅雨~夏に掛けて雑木林や広葉樹の樹液に集まるお馴染みの昆虫。
体の色はメタリック系の胴色から緑がかった物など様々。
昼間活動する昆虫で、強い大型甲虫類とは完全に住み分けしている様にも見える。
その為に天敵の鳥類に襲われにくい様に日光が当たると光輝いて鳥の警戒色を発すると言われている。
タマムシ同様に『構造色』の昆虫。
また有害な直射日光を反射するとも言われる。
前翅(外の固い羽根)をたたんだまま後翅(内側の軟らかい羽根)を広げて飛行可能です。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
カナブンの取り扱いは御座いません。
●ミヤマクワガタ

甲虫目 クワガタムシ科
大きさ(野外品)・・・オス28~78mm、メス24~48mm
自然界での活動時期・・・6~9月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
6月の梅雨の後半から梅雨明け前後に標高がやや高い山地の雑木林で見かける事が出来る昆虫。
体の色が茶色っぽく、オスの体には金色の短い毛が生えている。
またオスの頭部は冠状に張り出しているのが特徴です。
メスは、アゴが太く裏返しにすると脚の付け根にオレンジの模様が有る。
名前の由来は、山奥=深山に生息する事から付けられている
夜行性の一面もあるが早朝や日没前の夕方にも活動する事から、他の昆虫達と活動時間をずらして上手く住み分けている様にも思える。
●ナナホシテントウ

甲虫目 テントウムシ科
大きさ・・・5~9ミリ
活動時期・・・3~11月(運が良いと1月でも晴れた日に見掛ける事が出来る)
分布・・・北海道、本州、四国、九州、沖縄
赤い羽根に7つの黒い紋があるお馴染みのテントウムシ。
派手な色は、鳥類等の外敵から身を守る為の物とされる。
丸くてコロコロとした可愛い姿で人気の昆虫。
成虫は枯れ草の根元や障害物の下で越冬する。
春になって暖かくなると草むらで大量に見掛ける事も出来る。
成虫、幼虫共に主にアブラムシを食べる。
手で触ると黄色の少し臭い液体を出す。
これも天敵から身を守る為の物とされている。(因みに人体には無害である)
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ナナホシテントウの取り扱いは御座いません。
●アカホシテントウ

甲虫目 テントウムシ科
大きさ・・・5~7ミリ
活動時期・・・4から10月
分布・・・北海道、本州、四国、九州、沖縄
光沢のある黒い体で翅の中心付近に大きく滲む様な赤い斑紋がある綺麗なテントウムシ。
外敵から身を隠す為に頭部を引っ込めた姿はテントウムシではない別の生き物と勘違いをするほど。
梅や栗等に付いたカイガラムシを補食する益虫。
幼虫もカイガラムシを補食し、そのまま枝先で集団でサナギになり5月頃に羽化する。
常に集団になって群集する幼虫やサナギの姿も未知の生物の様に毒々しく初めて見ると絶対にテントウムシだと分からない。(鳥から身を守る為の手段とされる)
梅の実の収穫時期に枝や葉っぱを注意深く探すと見付ける事が出来る。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
アカホシテントウの取り扱いはございません。
●コガネムシ

甲虫目 コガネムシ科
大きさ・・・17~25ミリ
活動時期・・・5月~8月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
新緑の季節から夏に掛けて雑木林の周辺や草むらで見かける事が出来る昆虫。
広葉樹の軟らかい葉っぱや草の葉を食べる。
鮮やかなエメラルドグリーンの色は、光の当る角度で様々な色にも見える。『草原の宝石』
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
コガネムシの取り扱いは御座いません。
●マメコガネ

甲虫目 コガネムシ科
大きさ・・・9~15ミリ
活動時期・・・5~10月(初夏~秋)
分布・・・北海道、本州、四国、九州
頭部から胸部が緑色で翅が光沢が強い緑~茶褐色の小型のコガネムシ。
主にマメ科、ブドウ科、バラ科の植物、広葉樹にも集まる。
果樹、野菜等の農作物や園芸植物の害虫としても知られる。
1本の植物に覆い被さる様に鈴なり状態で大量発生する事もある。
100年ほど前に輸出品に紛れ込みアメリカに侵入し、現在ではトウモロコシの害虫「ジャパニースビートル」として恐れられている。
名前の由来は、マメ科の植物に集まる事から。(マメの様に小さいからでは有りません。)
初夏の雑木林や果樹園などの若葉に集まっている光景を良く見掛ける。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
マメコガネの取り扱いは御座いません。
●シロテンハナムグリ

甲虫目 コガネムシ科
大きさ・・・15~26ミリ
活動時期・・・5~9月
分布・・・本州、四国、九州
緑~胴色の褐色の体に小さな白い斑点模様を持つ大型の綺麗なハナムグリ。
ハナムグリという名前とは裏腹に夏が近付くと雑木林の広葉樹の樹液に集まる光景を頻繁に見る事が出来る。
産卵は、写真の様に腐葉土に行なう。
羽化後、蛹室(土繭)の中で長期間の休眠の後に活動をすると思われる。(春先の肌寒い季節に土中より新成虫を発見)
カナブンやハナムグリの仲間は、前翅(硬い翅)を閉じたまま高速飛行が可能である。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
シロテンハナムグリの取り扱いは御座いません。
●ハナムグリ(ナミハナムグリ)

甲虫目 コガネムシ科
大きさ・・・14~20ミリ
活動時期・・・4~7月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
名前の通り、春になって花が咲く頃に花粉を食べる為に集まる姿をよく目にする。白い斑点が有る緑色の綺麗な昆虫。
何故かハナムグリの仲間は、ヒメジョオン等の白い花びらで黄色い花粉を持つ花に集まる。
白い花が咲く花壇や公園でも普通に見付ける事が可能。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ハナムグリの取り扱いは御座いません。
●クロハナムグリ

甲虫目 コガネムシ科
大きさ・・・11~15ミリ
発生時期・・・4~8月
分布・・・北海道、本州、四国、九州、沖縄
黒い体に翅の中央付近に帯状にクリーム色の斑紋がある小さなハナムグリ。
気温が上がり始める4月下旬から5月に掛けて徐々に姿を現す。
勿論、他のハナムグリ同様に幼虫時代は、腐葉土や柔らかい朽ち木を食べて育ち、成虫は花の花粉を食べる。
ハナムグリの仲間は秋に羽化して蛹室の中で越冬後に活動して寿命を終える事が多い。
成虫は公園や庭の花壇や野原で比較的簡単に見掛ける事が出来る。
初夏の暖かい日に沢山のハナムグリ達が集まるり賑やかになる事もある。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
クロハナムグリの取り扱いは御座いません。
●ヨツボシケシキスイ

甲虫目 ケシキスイ科
大きさ・・・7~14ミリ
活動時期・・・5~8月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
梅雨~夏に掛けて雑木林の広葉樹の樹液に集まる小型の昆虫。
光沢のある黒い体で羽根に左右に各2個(計4個)の赤い星形の斑紋がある事が「ヨツボシ」の名前の由来。
ケシキスイの仲間は、クアゴ(頭部や口が発達した物ではなく独立の部位=武器)を持つ昆虫でエサ場やメスを求めてオス同士で喧嘩をする事で知られている。
成虫で越冬出来るので冬でも樹皮の裏に隠れている事が多い。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ヨツボシケシキスイの取り扱いは御座いません。
●ヨツボシオオキスイ

甲虫目 オオキスイムシ科
大きさ・・・10~15ミリ
活動時期・・・5~8月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
梅雨~夏に掛けて雑木林の広葉樹の樹液に集まる小型の昆虫。
体は黒く翅に左右2個ずつ計4個の黄色い紋がある。
同じ場所に棲息するヨツボシケシキスイの様な体の丸みは無く平べったく長細い体型をしている。
樹皮や樹洞の隙間に巧みに入り込み、大きな昆虫を巧みに避ける様に樹液を吸う姿を良く見掛ける。
ヨツボシケシキスイと並び樹液に集まる昆虫の代表格です。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ヨツボシオオキスイの取り扱いは御座いません。
●ゲンジボタル

甲虫目 ホタル科
大きさ・・・10~16ミリ
活動時期・・・6~7月
分布・・・本州、四国、九州
6月上旬の梅雨入り前後に夜になると綺麗な水辺の周辺で発光する昆虫。
光で求愛の交信をしていると言う説も有る。
日本最大のホタルで最も強い光を発する。発生ピーク時の星空の様な綺麗な光景は見物する価値がある。
梅雨に入り大雨が降り出す頃には、短い生涯を閉じて数か少なくなる為に儚さの象徴的な昆虫でもある。
幼虫は、カワニナ(巻貝)を食べて育つ。因みに幼虫も発光する。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ゲンジボタルの取り扱いは御座いません。
●ヘイケボタル

甲虫目 ホタル科
大きさ・・・6~10ミリ
活動時期・・・6~8月
分布・・・北海道・本州・四国・九州
6月上旬の梅雨入り前後から水辺(池や沼、水田などの止水域)で見掛ける事が出来るゲンジボタルよりも少し小型のホタル。
胸部が赤く中央に黒いスジ状の太い模様が入る
ゲンジボタルと違い止水域で育つので川が無い山中寄りの場所で見掛ける事が多い。
ホタルの仲間は、夜に光で求愛の交信をしていると言う説も有る。
初夏に集中的に発生するゲンジボタルに対してこちらは、夏季の長い期間に渡って少しずつ発生する。
点灯する速度も小刻みで早く光で種類の区別をする事も出来る。
平安時代末期の源平合戦の源氏(ゲンジ)と平家(ヘイケ)が名前の由来。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ヘイケボタルの取り扱いは御座いません。
●ジョウカイボン

甲虫目 ジョウカイボン科
大きさ・・・15~18ミリ
活動時期・・・4~8月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
初夏から夏に掛けて草むらや雑木林で見掛ける事が多い昆虫。
黒い頭部と赤茶色の長い触角と柔らかい翅が特徴で一見カミキリムシの仲間に見えるが別種(ホタル上科に近い)。
成虫、幼虫共に他の昆虫を補食する肉食系の昆虫で飛行性も非常に高く、飛び回る事が多い。
名前の由来は、風を表す言葉や平清盛の仏名からだと諸説様々だが不明である。
軽やかに草木の葉っぱを飛び回る姿を良く見掛ける。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ジョウカイボンの取り扱いは御座いません。
●ラミーカミキリ

甲虫目 カミキリムシ科
大きさ・・・8~17ミリ
発生時期・・・5~7月
分布・・・九州、四国、本州(西日本に多い)
※外国からの移入種。
初夏にイラクサ科の植物(カラムシ、ムクゲ等)の軟らかい葉や茎を食べる姿を草むらで見かける事が出来る変わった色の小型のカミキリムシ。
明治初期に繊維作りの為に輸入された植物のカラムシ(ラミー)にくっ付いて日本にやって来た事が名前の由来。
水色と黒のパステル調の綺麗な模様が特徴。
飛行性が高く意外と俊敏。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ラミーカミキリの取り扱いは御座いません。
●シロスジカミキリ

甲虫目 カミキリムシ科
大きさ・・・45~60ミリ
発生時期・・・6~8月
分布・・・九州、四国、本州
灰色の体に白~黄褐色の筋が縦に入っている事が名前の由来。
国内最大種のカミキリムシでキバの力も強く固い樹皮にも簡単に穴をあける。
成虫は、主に広葉樹の雑木林に棲息して生木の小枝や新芽を食べる。
やや夜行性の傾向があるが早朝や夕方にも姿を現す。
産卵は、梅雨入り後に広葉樹の樹皮を齧って行なう。(写真の状態)
産卵時に傷付けられた樹皮や幼虫が食べた後の幹の穴や成虫の脱出口から大量の樹液が出る。
その様な自然のメカニズムを考えると夏に樹液に集まる昆虫と切っても切れない不思議な関係がある。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
シロスジカミキリの取り扱いは御座いません。
●ミヤマカミキリ

甲虫目 カミキリムシ科
大きさ・・・35~57ミリ
発生時期・・・6~8月
分布・・・北海道、九州、四国、本州
黄土色(くすんだ茶褐色)の大型のカミキリムシで胸部にシワが有るのが特徴。
真夏の夜間に広葉樹の樹液を吸う姿をよく見掛ける事が出来る。
名前の由来は、深い山に生息する事から付けられている。
産卵は広葉樹の樹皮の裂け目やくぼみに行なう。
幼虫は、生木を食い進みながら成長して行く。
カミキリムシの食痕や脱出口からは夏になると樹液が出て様々な昆虫達が集まると言う自然のメカニズムが有る。
羽化した成虫は、そのまま広葉樹の樹液に集まる。
1本の木に何匹も集まっている事が多い。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ミヤマカミキリの取り扱いは御座いません。
●ゴマダラカミキリ

甲虫目 カミキリムシ科
大きさ・・・25から35ミリ前後
活動時期・・・5から8月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
黒い羽根に白い点のまだら模様が入ったカミキリムシ。
体の1.5倍以上ある長い触角は白と黒の縞模様をしていて、脚は青っぽい色をしている。
初夏から夏に掛けて雑木林や公園や庭の樹木付近で見掛ける事が出来る。
街路樹や果樹の害虫として扱われる事もある。
成虫・幼虫共にクリやヤナギなどの樹木を食べる。
新成虫が脱出した際に出来た樹皮の穴から樹液が出て昆虫が集まる。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ゴマダラカミキリの取り扱いは御座いません。
●ホシベニカミキリ

甲虫目 カミキリムシ科
大きさ・・・18から25ミリ前後
発生時期・・・5月下旬~7月上旬(七夕前後の頃迄)
分布・・・本州、四国、九州、その他離島
鮮やかな紅色の体色で翅に大小様々の楕円形の黒い斑紋を持つカミキリムシ。
名前の由来は、見た目に由来する。
脚や長い触角は黒い。
成虫は、初夏に【タブの木(タブノキ)】で見掛ける事が出来る。
主にタブノキの葉や若い(柔らかい)緑枝を食べる。
産卵もタブノキに行い、樹皮を楕円形(卵の形)に綺麗に齧って剥がして産卵床を作り円内に複数産卵するのが特徴。
幼虫もそのままタブノキの生木を穿孔して食い進む。
実は、タブノキはクスノキ科の常緑樹だがホシアカカミキリが齧った痕や幼虫の食痕(虫糞孔:糞や木屑を出す穴)から大量の樹液を出す為、様々な昆虫が集まる知る人ぞ知る木。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ホシベニカミキリの取り扱いは御座いません。
●センノキカミキリ

甲虫目 カミキリムシ科
大きさ・・・20~40ミリ前後
発生時期・・・6~8月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
茶褐色の体に薄くて黒い斑紋が複数ちりばめられた、やや大型のカミキリムシの仲間。
成虫は、タラノキ、ヤツデ、センノキ(ハリギリ)などのウコギ科の植物に集まる。
※上記のセンノキという植物に集まる事が名前の由来。
成虫は、これらの植物の柔らかい樹皮や葉柄(葉っぱの茎)を食べる。
勿論、産卵も同様の樹木に行われ、幼虫も幹や茎の内部を食べて育つ。
梅雨入り以降に発生して、日中でも活動する昆虫なので注意深く探すと比較的簡単に見つける事が出来る。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
センノキカミキリの取り扱いは御座いません。
●ウスバカミキリ

甲虫目 カミキリムシ科
大きさ・・・30~55ミリ
発生時期・・・6~8月
分布・・・北海道、九州、四国、本州、沖縄
鈍い褐色の翅が柔らかいカミキリ。(羽根が薄くて柔らかい事が名前の由来)
体は細長く一見すると弱々しく感じるが気性は荒い。
主に雑木林に棲息し、主に広葉樹に集まる。
夜行性の昆虫で昼間は樹皮や根元の窪みに隠れている。
街灯にも誘われて集まって来る事が有る。
広葉樹や果樹の生木や倒木に産卵をして幼虫もそれらをを食べて育つ。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ウスバカミキリの取り扱いは御座いません。
●オオゾウムシ

甲虫目 オオゾウムシ科
大きさ・・・12~25ミリ
活動時期・・・5~9月
分布・・・北海道、本州、四国、九州、沖縄
黒~茶、灰褐色をした日本最大級のゾウムシ。
体に黒や灰色の縦方向のまだら模様がある。(写真の個体の様に体色と樹皮の色が酷似する物もいる)
体はゴツゴツとして固く動きは遅い。
名前の由来は、姿のとおりゾウの鼻の様に長い口を持っているからである
夏場に主に雑木林の広葉樹などの樹液に集まる。
ビックリすると木から落ちて、ひっくり返って死んだ振りをする面白い一面もある。
見掛けに寄らず飛行性も強く街灯の明かりにも集まる。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
オオゾウムシの取り扱いは御座いません。
●サビキコリ

甲虫目 コメツキムシ科
大きさ・・・15ミリ前後
発生時期・・・5~9月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
錆の様なつやの無い褐色とザラザラとした体が特徴のコメツキムシの仲間。頭部が小さく胸部が幅広なのも大きな特徴。
体色の濃淡や模様に若干の個体差が有る。
雑木林や森で普通に見かける事が出来る昆虫。
また、街灯や民家の灯りに飛来するので網戸にくっ付いている事も多い。
この虫は、ひっくり返すとパッチンという音を立てて表向きになるのでお子様と一緒にふれ合っても面白い昆虫。
※本来は、外敵が近付くと脚を竦めて逆さになってやり過ごす為の行動。色が錆色なのも樹皮や土に似せる為。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
サビキコリの取り扱いは御座いません。
●フタモンウバタマコメツキ

甲虫目 コメツキムシ科
大きさ・・・26~33ミリ
発生時期・・・4~9月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
木の樹皮に似た黒、茶~灰色、黄褐色の体色が特徴の忍者の様な昆虫。
ウバタマコメツキとよく似ているが翅の両側に二つの黒紋がある。
コメツキムシの仲間では大型種になる。
成虫は主に雑木林や広葉樹の樹液で見かける事が出来る
幼虫がマツの朽ち木の中で他の昆虫の幼虫を食べて育っている事からマツ林に近い場所に多く生息する。
したがって海岸近くの松の防風林に隣接した雑木林では個体数が多くなる。
ひっくり返ると発達した胸部の筋肉で反動を付けて大ジャンプをして起き上がる。(子供に見せてあげたい昆虫)
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
フタモンウバタマコメツキの取り扱いは御座いません。
●ヒゲコメツキ

甲虫目 コメツキムシ科
大きさ・・・20から30ミリ前後
発生時期・・・5~8月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
赤茶色で体中が微毛に覆われた大型のコメツキムシ。
上翅に斑状の模様が入る。
オスは、櫛状に広がった立派な触角を持っており派手な見掛けをしている。
一方、メスは画像の様にノコギリ状の触角で少し見かけが地味になる。
成虫は雑木林や山林の樹上でエサの小さな昆虫を補食して過ごす。
勿論、コメツキムシなのでひっくり返すとパチンという音を立てて起き上がる。
気性が荒い個体は、周囲に昆虫が近付くとパチン、パチンと音を立てて威嚇する事も確認されている。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ヒゲコメツキの取り扱いは御座いません。
●オオクロクシコメツキ

甲虫目 コメツキムシ科
大きさ・・・15から17ミリ前後
活動時期・・・5から8月
分布・・・本州、四国、九州
梅雨~夏に掛けて草むらや雑木林、畑や花壇などで見掛ける事が出来る昆虫。
黒くツヤがある体に黄色っぽい微毛が特徴のコメツキムシ。
コメツキムシの仲間は、ひっくり返ると「パチッ」という音を立てて勢い良く跳ねて起き上がる。
この動作と米つきの様子が似ている事から「コメツキムシ」と呼ばれる。
植物の葉っぱの上に止まっている事が多いので草食の様に思えるが実は肉食昆虫で小さな昆虫を補食する。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
オオクロクシコメツキの取り扱いは御座いません。
●ヒメクロオトシブミ

甲虫目 オトシブミ科
大きさ・・・4~5ミリ
活動時期・・・4~8月
分布・・・本州、四国、九州
黒い色をした胴体が丸く首が短いオトシブミ。
腹部と脚部が真っ黒の物と赤褐色のパターンの個体が存在する。
一般的に西日本(関西より西)の地域の物が赤褐色の物が多いとされる。(写真の個体は福岡県福津市にて撮影した物なので脚が赤い)
初夏~夏に掛けて広葉樹などの新緑の葉の先端を葉巻状にクルクルと巻いて卵が入った揺りかごを作る。
「オトシブミ」の名前の由来は、この形状が平安時代の恋文(落とし文)に似ているからです。
広葉樹の葉っぱの先端を必死に丸める姿や小さな丸められた若葉を見掛ける事が出来る。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ヒメクロオトシブミの取り扱いは御座いません。
●ニワハンミョウ

甲虫目 ハンミョウ科
大きさ・・・15から19ミリ前後
活動時期・・・4から10月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
名前のとおり庭や山間部などの草が生えていない日当りの良い乾燥した箇所の地面を徘徊する昆虫
ハンミョウと言えば綺麗な昆虫をイメージするがニワハンミョウは、暗い銅金色の体に翅の左右に白い斑紋がある。(斑紋の数や形は地域変異や個体差が大きい)
ハンミョウの仲間は動きは速く、短い距離を小刻みに前方へ飛んで逃げて行くので通称:道案内、道教え、道しるべなどの呼ばれ方をしている。
幼虫成虫共に肉食で小さなアリ等の昆虫やミミズを食べる。
幼虫は地面に穴を掘って近付く獲物を待ち構える
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ニワハンミョウの取り扱いは御座いません。
●ユミアシゴミムシダマシ

甲虫目 ゴミムシダマシ科
大きさ・・・25から27ミリ前後
活動時期・・・5から8月
分布・・・本州、四国、九州
初夏から夏に雑木林でよく見掛ける事が出来る昆虫。
黒い色をしていて背中には点刻がある。
前腕が弓なりに湾曲している事が名前の由来。動きは早くない。
本来は、広葉樹の枯れ木(朽ち木)に集まる昆虫だが枝枯れ部分にも集まるので生きた木を登る姿を良く見掛ける。(キノコの腐朽菌の臭い等を感知して集まる)
夏場の特に梅雨のジメジメした時期はキノコ等の菌類も活性するので最も活発に動き回る。
幼虫は朽ち木を食べる
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
ユミアシゴミムシダマシの取り扱いは御座いません。
●キマワリ

甲虫目 ゴミムシダマシ科(キマワリ亜科)
大きさ・・・15から20ミリ前後
活動時期・・・5から10月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
初夏から夏に雑木林でよく見掛ける事が出来る里山の昆虫。
黒く丸みを帯びた体型をしたゴミムシダマシの仲間。上翅には、くっきりとした点刻が有る。
脚はカナブン等のコガネムシ科の昆虫よりも長い。
夏の夜間に広葉樹の幹や枝の他に朽ち木の倒木の上を歩いている姿をよく見掛ける。
木の幹を素早くグルグルと回る様に移動する事が名前の由来。
見掛けによらず動きが素早い。
幼虫は、原木椎茸の朽ちたホダ木を食べて暮らしている事から上手く人間社会(農林業)と共生している様にも思える。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
キマワリの取り扱いは御座いません。
●オサムシ

甲虫目 オサムシ科
大きさ・・・23~38ミリ
発生時期・・・4~10月
分布・・・本州、四国、九州
4月になって雨が多くなる頃から森林や草むらで、よく見かける昆虫。
夜行性とされるが雨上がりに見かける事も出来る。
オサムシの仲間は飛行能力が全く無い物が多いが、オオオサムシも例外では無い。
よって、移動は地面を歩行するのみで、地上に出てきたミミズや小さな昆虫の幼虫を主食とする。
寿命が長く越冬して複数年生きる。
水没しても仮死状態で耐えて時間をかけて蘇生をする事が多い。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
オサムシの取り扱いは御座いません。
●マイマイカブリ

甲虫目 オサムシ科
大きさ・・・26~70ミリ(地域差が大きい)
活動時期・・・4~10月
分布・・・北海道、本州、四国、九州
日本固有の首の長い大型のオサムシ。
体の色は、亜種や地域間での差が大きく、一般的に西日本や九州の物は光沢が無く真っ黒の個体が多い。
名前の通り梅雨~夏に掛けて草原や森でカタツムリの殻に頭を突っ込んで食べる。
その他にも雨上がりに地表に出てきたミミズを食べる姿を良く見掛ける。
長い首は、カタツムリを食べるのに役立つ。
夜行性で夏に樹液を吸う姿を頻繁に見掛ける。
外敵が近付くとお尻から強い刺激性のガスを発射するので絶対に触ってはいけない昆虫。
手に掛かっただけで火傷をした様な強い刺激が有るだけでなく、目に入ると炎症を起す危険性がある。
他のオサムシ同様に下翅が無く空を飛ぶ事が出来ない。
その為、歩行で移動する事しか出来ない。
調査目的で環境指標種として扱われる事も多い。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
マイマイカブリの取り扱いは御座いません。
●オオヒラタゴミムシ

甲虫目 オサムシ科(ナガゴミムシ亜科)
大きさ・・・11から16ミリ前後
発生時期・・・3~11月
分布・・・北海道、本州、四国、九州、沖縄
草むらや森で地表や樹上にいる事が多い肉食系のゴミムシの仲間。
艶が有る黒い体色で胸部が極端に細く胸部の側面と脚の先や触角が赤褐色(オレンジ色っぽい)のも特徴。
本来はオサムシ同様にミミズの死骸や柔らかい昆虫等を食べるが画像の様に広葉樹の樹液に集まる姿を見掛ける事も出来る。
夜行性の昆虫で夜間や薄暗い時間帯に活発に動き回る。
昼間は枯れ草の下や草の根っこ付近に隠れている事が多い。
灯火に飛来する習性が有り街灯うあ民家の照明にも集まって来る。
オサムシと違って飛ぶ事が出来る昆虫。
※このページは、里山の昆虫を紹介する為の図鑑です。
オオヒラタゴミムシの取り扱いは御座いません。



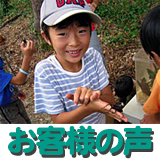








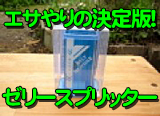
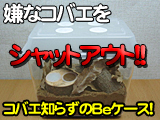


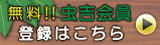







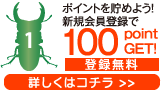
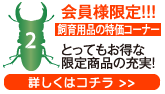
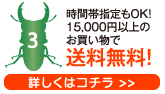
































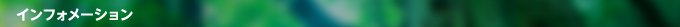


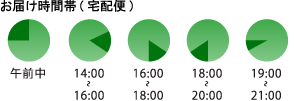
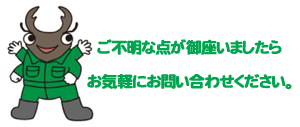

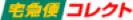



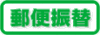
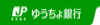
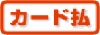
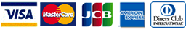
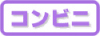
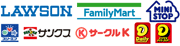

 当サイトはベリサイン社のデジタルIDにより証明されています。 データ入力、送信は、SSL暗号通信により、お客様のウェブブラウザーとサーバ間の通信がすべて暗号化されるので、ご記入された内容は安全に送信されます。
当サイトはベリサイン社のデジタルIDにより証明されています。 データ入力、送信は、SSL暗号通信により、お客様のウェブブラウザーとサーバ間の通信がすべて暗号化されるので、ご記入された内容は安全に送信されます。 